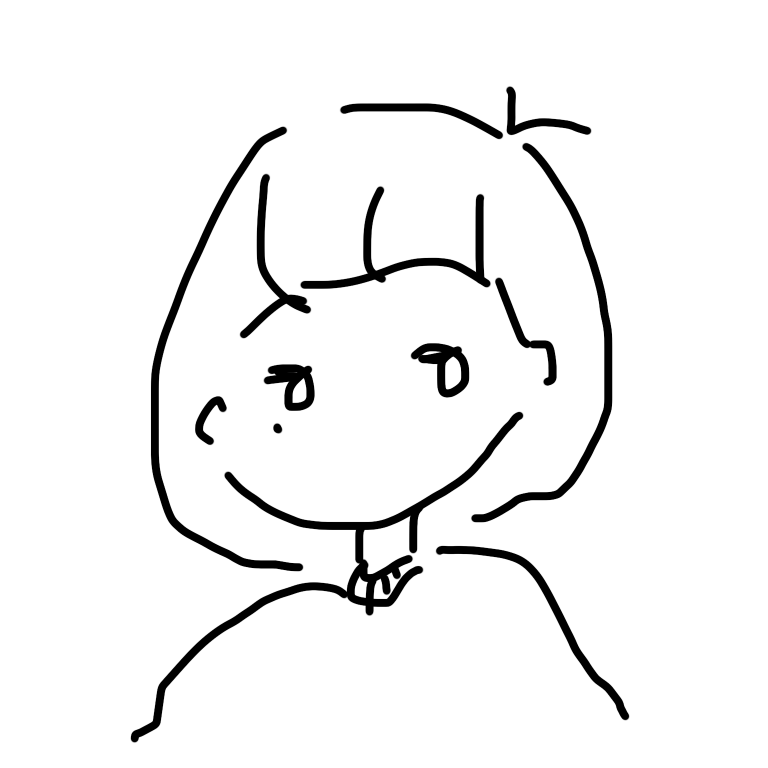-

月燈町表通り
¥300
ちょっと懐かしい架空の町、「月燈町」を舞台にした小説集。 2025年5月に発行した『月燈町表通り前日譚』の続編にあたる第2巻ができました! 連作ですが、内容は独立しており、この本だけでお楽しみいただけるようになっています。 ※ 数に限りがありますが、『前日譚』もあわせて頒布予定です 〈収録〉 ・月燈町へ流れついた直野は、ひかりロード商店街の弁当屋でアルバイトをしている。 ある秋の日、幼馴染の愁と再会し、クリスマスを一緒に過ごす約束をするが……(夏野サカリ「冬のなか」) ・先輩の恒平が倒れたと聞き、剣持は月草荘へかけつけた。隣人の美潮さんは、恒平の後ろに花が見えると言って……(幅観月「花のひと」) 42ページ 装画 ト・ウコ
-

短文集・いつか神様になったら
¥500
「目って閉じたら開くんだよ。こわくない」 # 夕方の五時に起きると、自分が今までとは別の世界にいるんじゃないかと錯覚する。けれど陳腐な幻想は部屋干ししたでろでろのティーシャツの臭いに一瞬でかき消されてしまう。その日もそうだった。「今日、十八時半でよろしくね」なんてメールを開いてしまったから、最悪。 「西口に何回か入ったことあるパスタのお店があるんだけど」 そのセリフを聞いたとき、起床から二時間もたっていない頭で「あ、こいつだめだ」と思った。 ~~~ 「いつか神様になったら」は2016年初出の短編小説です。2019年発行の『想像上の路地』にも掲載しました。 いまはどちらも頒布していない本です。 今回、表題作を中心に、tumblerに載せた短い文章などを集めてみました。 いつか神様〜は2016年版をほとんど改稿せずに載せています。 新書判、32ページ、角丸加工
-
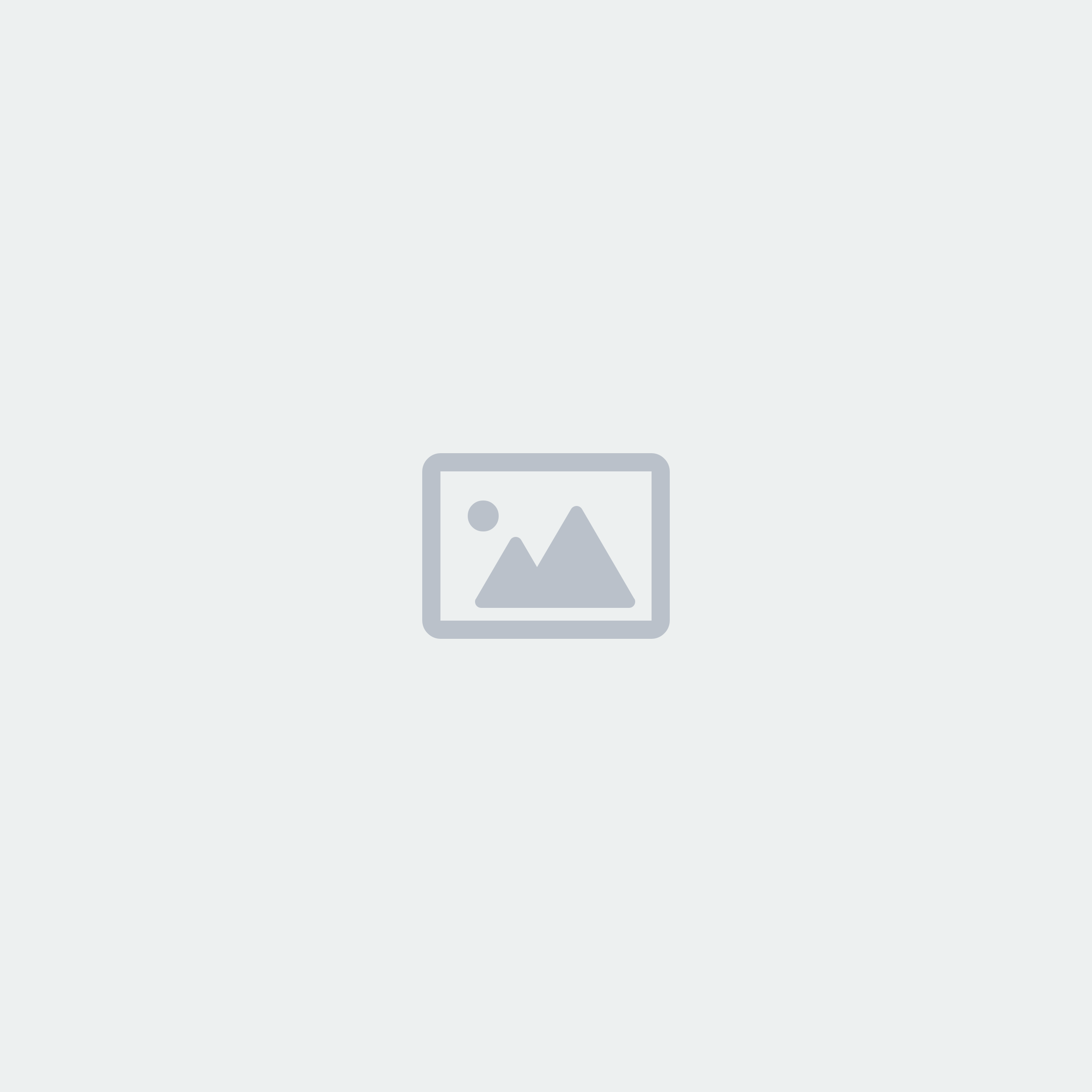
月燈町2巻セット
¥500
SOLD OUT
・月燈町表通り〈前日譚〉 ・月燈町表通り の2巻セット 連作なので、続きものとしてお読みいただけます 通販では2巻セットの方が少しだけリーズナブルになっています
-

想像上の路地2(ツー)
¥850
想像上の路地は、架空の町をつくっていく本です。 『想像上の路地』から5年あまり…… このたび『想像上の路地2(ツー)』を刊行します! 小説、論考、漫画、日記…etc 素敵なゲストのみなさまとお送りいたします。 ひろがってゆく町、 そこはちょっとふしぎなユートピア。 たまに暮らして、たまに迷って、たまに眠って、夢をみて。 想像上の路地へようこそ。ぜひきてください。 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜 はじめに 風景へ 勝見里奈 図らずも観光客 佐藤述人 走らない冬 幅 観月 わたしたちシリーズ ピーチメルバと自由の混乱 ト・ウコ Deer in the park 大山 海 伏梁と放火の関連性についての考察 山本貫太 ウォッカ きくち 午後二時の図書館 吉井アキオ いっしょに逃げよう おかっぱのねえね Wink 幅 観月 ●表紙写真 勝見里奈 想像上の地図付き! (照らし合わせて本を楽しめます) A5判、116ページ
-

月燈町表通り前日譚
¥300
SOLD OUT
知らない町、だけど月燈のような優しさと懐かしさがここにあるーー 想像上の路地の隣町、「月燈町表通り」を舞台に巻き起こる物語 今回はその「前日譚」をお届けします。 ・ひかりロード商店街にある弁当屋「清」で働く、ちょっと内気で天邪鬼な直野。 兄弟思いで面倒見のよかった4つ上の幼馴染・愁は、大学卒業とともに上京してしまいました。 彼のあとを追って上京した直野は、公園で弁当を食べながら彼のことをふと思い出し……? 「はるのなか」夏野サカリ ・お人好しの大学生・柚木は知らないうちに花見会の場所取り係なって、朝からレジャーシートに寝転がっています。 ちょっとした災難にあい、傷だらけの体で…… そこに高校からの後輩・剣持が現れ、あっさりケガを見抜かれてしまい……? 「薄荷ブルー・キャンディ」幅観月 人と人との関係にフォーカスを当てた上記の小説を2篇収録。 「温度」を感じることのできる手作り本、 部数限定の販売です。 表紙の消しゴムはんこ作品はト・ウコ氏。 ぜひお手にとってご覧ください。 B6判、20ページ
-

春、きみの指が燃えていたこと
¥600
SOLD OUT
大学時代にかいた掌編〜短編に加え、書き下ろし(「春、きみの指が燃えていたこと」)を収録。 新書版 82ページ ※ 初版、2刷完売、3刷になります。 〈収録作品〉 ・かからない魚 ・春、きみの指が燃えていたこと ・クリーム ・とおい夢 ・慈雨のこと ・coke ・女神におねがい (以下、「春、きみの指が燃えていたこと」試し読みです。) 「いくら考えてもわからないことがある。 二十一歳の春、永はいなくなった。誕生日が九月の彼女はまだ十九歳だった。その日も一緒に泳ぐ約束をしていた。いつもなら十一時ごろに来て一、二本流していると自然と落ち合えるはずが、彼女はいつまでたっても現れなかった。昼の休憩で監視員に声をかけられるまで、僕は仰向けでプールに浮いていた。」 * 永いはく、僕の顔は薄いけれど、あっさりとはしていない。素敵な生地で仕立てられたシャツみたいだ、とも言う。柄も形もありふれているのに、何度洗っても色褪せず、そっくりしている。そんなシャツ、いいなと思う。そしたら永は「ほら、ちょうどあなたが着ているみたいな」とつづけた。そこではじめて、自分が生成り色のリネンシャツを着ていることに気づく。僕は、服装にこだわりがあるほうではない。大学の講義があるときは襟付きのものを選ぶようにしているが、それはただ単に、気をつかわずともある程度きちんとしてみえるからだ。 ふと、つむじのあたりに熱を感じる。顔をあげる。視線が絡んだ。永の目の開き具合がわずかに悪くなる。僕はすかさず「ありがとう」と言う。 「そうやってすぐ適当に返事する」 永はテーブルに肘をつき、手の甲に頬をのせた。片方の手でバナナジュースにささったストローのさきをいじりつつ、今度はあきらかに僕をにらんでいる。また墓穴を掘ってしまった。 「わたしの話がつまらない、って風でもないのよね。そう、興味がないのよ。だけどそれって相手に対していちばん失礼なことだと思わない」 「ごもっとも」それ以外に返す言葉がみつからない。人と会話をするとき、僕はいつもおなじようなことに悩まされる。なにか言わなければならないとき、返答の選択肢がふたつ以上浮かぶことはまずない。だから自ずとたったひとつの選択肢に頼ることになるのだが、永にはこれがいいかげんに聴こえるらしい。実際、人の話に耳をかたむけることはさほど苦痛ではない。興味がない、というわけでもない。ただ言葉を求められると頭の中にある空洞をみつめることになる。そこに僕はわずかな陰影をみいだそうとする。せめてそういう努力はしている。 * 枕元においていたミネラルウォーターに手を伸ばす。口をつけるまえに「飲む?」と聞くが、永はなにも言わずに首を振った。彼女は本当に水を飲まない。 そのあと僕はネッシーの話をした。ダストピットにシールを貼ったのはきみじゃないのかと問うと、永はくつくつ笑った。そして右腕を顔の横につけてのばし、手首を八の字に回してみせた。ネッシー? うん。たまに指先を何度かあわせて、口を動かしているように見せる。 しばらくやって、永は飽きたのかつかれたのか、右腕をベッドにおろした。顔を壁のほうに向け、微動だにしない。ホットパンツからのびた足は白く、触らなくとも冷たかった。タオルケットをかけてやる。起きたらふたりでダストピットを見にいこうと思った。 今日はやはり水曜日だった。予感は当たっていた。
-

hug
¥500
書き下ろし「しじまに寄せて」ほか、4篇を収録した短編集『hug』 文庫判 72ページ ※2024.5.20追記 2刷になりました! 表紙の裏の遊び紙がグリーンのトレーシングペーパーに変更されています。 本文は初版と同一です。 収録 ・hug ・しじまに寄せて ・花の終わり ・エンゼル 以下、「しじまに寄せて」冒頭部分です。↓ 中学にあがってしばらくした頃、心の暗がりに迷い込んだ。迷子になったわたしの手をとり、帰り道を示してくれたのは伊織という男の子だった。 彼は体育館裏の階段に腰かけているわたしを見下ろしてしばらく黙っていたが、気を取り直したように、「先生が心配してるから戻ろう」と言った。同い年とは思えない、温度の低いのんびりとした声だった。わたしはほとんど引き寄せられるようにうなずいていた。 午後の校舎はひっそりとしていた。三十ちかくの教室があり、何百人もの生徒が五時間目の授業を受けているだなんて、信じられないくらいの静けさだった。風が吹き、スカートのうえに音もなく木の葉が落ちた。彼と話したのは、その日がはじめてだった。 校庭のほうからホイッスルの音がして、伊織はわたしに背を向けた。心なしか背筋が伸びたようだった。とっくに消えた音の気配を追うように、彼はしばらく空の低いところを見据えていた。いま思えば、空を見ていたわけではなかったかもしれない。 あの頃のわたしは、何かに取り憑かれているかのようだった。母親が学校に呼ばれて担任の先生と相談していたことも、気づかないふりをしていたけれど知っている。 大人たちはわたしを問いたださなかった。そのかわり、こちらに向けられる視線にはつねに不安の色がにじんでいた。まるで自分がこわれものになったような、奇妙な心地がした。実際、わたしの身にはちょっと奇妙なことが起こっていたのかもしれない。家ではふつうに話をする十三の娘が、外にでた拍子にぷっつりと黙り込んでしまう。どこの母親でもきっと心配する。いちばんにわたし自身、自分についてわかりかねていた。説明など求められようものなら余計に混乱しただろうから、無理に言葉にしないままでいられたのは幸いだった。 そしてもっと幸いだったのは、わたしを見つけてくれたのが伊織だったことだ。 あるとき彼は、 「諏訪を呼び戻しにいったのは学級委員だったからだよ」 と言った。そうでなければ、わざわざ話しかけたりしなかった、と。 「いまにも噛みついてきそうな、犬みたいな目をしてた」 まさか、と思うが、当時の写真を見返してみると、わたしはたしかに性格のわるい犬のような目つきをしていた。これには面食らった。自分はおそらくかなり愛想のわるい部類の人間なのだ。 わたしと伊織はたいていの場合、図形を描くうえで正反対の位置にいた。彼はいつだって誰かしらに囲まれていた。彼らのまえで、伊織はよく笑った。意図せず多くの人の心を救うような笑顔だった。そこにいるだけで空気をやわらかく解きほぐしてしまう人というのは、たしかに存在する。光はどんな人にも平等に降り注ぎ、わたしの心をも掬いあげた。 * 大雨の降る十月のある夜、アルバイトから帰ってアパートの階段を上がると、玄関の前に人がうずくまっていた。髪の毛から雨粒が垂れ、傘もレインコートも持っていない。それにひどく薄着だった。水を吸ったティーシャツが皮膚に張りつき、その体は小さく震えていた。 ゆっくりと近づき、伊織、と呼んでみる。声は雨音にかき消された。わたしはポケットのなかで部屋の鍵を握りしめたまま、しばらくそうして立っていた。彼の二十一の誕生日が近づいていた。
-

ラッキーを頼むよ
¥400
七月最後の登校日、ふり向いた慈雨はわたしの知らない顔をしていたーー 慈雨は引っ越しの準備がたいへんだということと、お父さんが何度か荷物を取りに車で来てくれるのだということを言った。うちは車がないから、車で三十分の距離、というのが近いのか遠いのかよくわからなかった。でも学校を移るってことは遠いってことなんだろう、とひとりで納得して、なにかに抵抗するみたいにガードレールの外側を歩いて帰った。 14才、慈雨がいなくなる夏。 ~ 2024.5.19文学フリマ38初売りの新刊です 文庫判/38ページ 書き下ろし 中学生の女の子、清乃の夏休みのお話です 楽しい夏休みのはずが、同じマンションに住む慈雨が引っ越すことを知って…… だらしなくて切なくて、でも読んだらハッピーになれる、あっという間に過ぎる夏みたいな小説 短めなのではじめましての方もぜひお手にとっていただけたら嬉しいです
-

中華アンソロジー びゃんびゃん
¥650
ピータンがゆ、中華そば、餃子、肉まん、辣子鶏、ビャンビャン麺…… さまざまな「中華料理」をテーマに、四名の作家が描き出す、空腹を満たすこと必至の小説とエッセイを八篇収録したアンソロジー。 ビャンビャン飛んでいきましょう、「びゃんびゃん」の世界へ……。 B6判 126ページ 執筆陣(敬称略) 大滝のぐれ 小説「犬川〈いぬかわ〉のほとり」 セイコの飼っているラーメンどんぶりからビャンビャン麺が生えてきた。そのかぐわしいにおいにつられ、犬人間たちが彼を食い尽くすべく迫りつつあった。 においを遮断するふたを買いに行くため、セイコはラーメンどんぶりを抱え川沿いへと繰り出す。そこでまじわる、過去の情景と今の景色。それでもなお地続きであることについて。 幅観月 小説「夜の幽霊」 押し入れで寝起きする中学生の航。同級生のシーナは、中華料理店「永楽」で居候をしている。『おれは怖いんだ。いままでしてきたことと、これからしていくこと、全部に理由をつけなきゃならないと思ったら』――押し入れには、父さんの布団が冷たくなって眠っている。 ハスミケイ 小説「センチュリーエッグ」 「おれ」と暢子は毎週せまいキッチンに並んで料理をする、それはおさない罪悪の記憶をふくんだピータン粥だ――。理不尽さに抗う友情と、やわらかな味わいのピータン粥が百年先もそこにありつづけるであろうことについて。 佐々光 小説「アイ・ラブ・ギョーザ」 小学一年生の自分の夢が「うつのみやぎょうざ」だったことを知った由佳は、彼氏の啓介とともに宇都宮の街にやってきた。果たして彼女は、数多の種類が存在する宇都宮餃子の中から、自分のなりたかったたった一つを見つけ出すことができるのか! 表紙イラスト 横谷